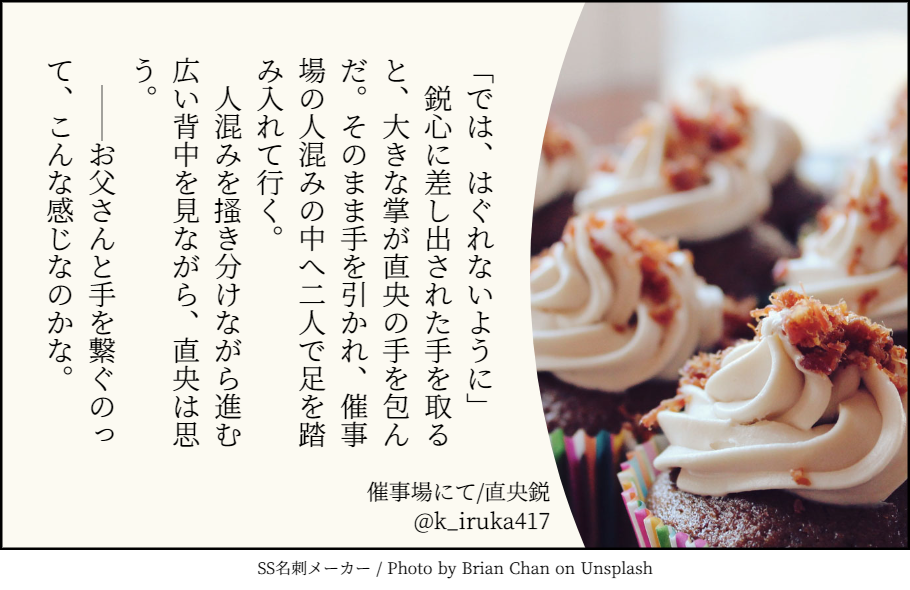天地四心伝丹碧の乱の後日の話。
◆◆◆
「昨日、雪之助が君の教育係を辞したよ」
先の戦いで重傷を負った教育係・雪之助が数ヵ月の療養を経て今日から復帰すると知らされていつもの稽古場で待ち侘びていた海月の前に現れたのは、養父・蒼生の右腕である沖之丞であった。
雪之助の療養中に雪之助に代わり剣の稽古を受け持っていた沖之丞は、動揺する海月に向けて淡々と告げる。
「彼は昨日の夜に蒼生と僕のところに来てね。今の自分には教育係として海月と顔を合わせる資格はないから、と」
「そんな……」
海月は言葉を失う。
ほんの数日前に会った時の雪之助は顔色も良く、既に怪我は完治しているように見えた。
久しぶりに雪之助と手合わせが出来ると、沖之丞に鍛えられ少しは強くなった自分を見てもらえると楽しみにしていたというのに、雪之助が自ら姿を消してしまうなど。
だがすぐに海月は思い至る。先の戦いの中で発覚した義理の叔父・白波の人間族に対する背信行為。そしてその中で、実は雪之助の父と師匠の死に白波が関わっていたのだと。
それを知ってからも雪之助は変わることなく海月に接していた。だが胸中決して穏やかではなかった筈だ。もし何か思い詰めているのだとしたら……
「っ……俺、雪之助を探して来る!」
取るものもとりあえず、海月は駆け出した。沖之丞は稽古場を飛び出していく海月を止めることなく、その背を見送った。
海月はと言うと、稽古場を飛び出してみたはいいものの、雪之助の行く先の心当たりなどなかった。
とりあえずは、ここで何か手掛かりを得ることが出来ればと雪之助の実家に足を向ける。見舞いのために何度も──それこそ二日に一回という頻度で訪れていた家だ。城からの行き方など勝手知ったるものである。
雪之助の家は古い屋敷である。そこに数日に一度通って来る小間使いを雇って掃除や雪之助一人では手の回らない部分の維持を任せているのだという。
正門から屋敷の中に足を踏み入れ、裏手の庭の方へと足を向けてみる。
すると目に飛び込んできたのは、掘り起こされて土の黒が露出した庭、その端で鍬を持ってせっせと土を掘り起こしている……雪之助の姿だった。
「……何やってるんだよ?!」
思わず声を上げると、雪之助が顔を上げた。農作業用であろう着物は泥だらけで、顔にも少しばかり土汚れが付いている。
雪之助は海月の姿を認めると「うわ」と顔を歪めた。
「何しに来たんだよ」
「何って……」
探しに来た自分がおかしいとでも言わんばかりの雪之助の顔を見て、思わず頭に血が上る。
「急にいなくなるから探しに来たんだろ!」
「いなくなるって……」
雪之助は眉をひそめてから、はあ、と大きなため息を一つ吐き出した。何か呟いたようだが、海月には聞こえなかった。
「何か言った?」
掘り起こされた土は踏まないようにしながら雪之助に詰め寄ると、雪之助は首を横に振った。
「別に何でもないよ……ったく。お前暇なの?俺がいなくても学ぶべきことは沢山ある筈だし、剣術の稽古なら沖之丞さんに付けて貰ってるだろ」
「それは雪之助が復帰するまでの期間限定!俺はまだ雪之助から一本も取ったこと無いし、第一沖之丞さん強いけど教えるのは下手だし自分でも言ってたし……とにかく、なんで急に辞めるなんて言い出したんだよ。俺と顔を合わせる資格がないって、どういうことだよ」
「そのままの意味だよ」
雪之助はまた鍬を動かし始めた。
「俺は当分真っ当に生きるのは無理だなと自分で思ったから、お暇をいただくことにした。一人で考える時間が欲しかったんだ」
真っ当に生きるのは無理。そんな重い言葉がさらりと雪之助の口から出たことに、海月は心の臓を鷲掴まれたような心地がした。
「……一人で考えて、雪之助はそれでいいの」
「……それでいいからそうしてるんだけど。何が言いたいわけ」
雪之助の声の温度が下がる。ここで言葉を間違えればきっと俺はこの家から放り出されるし口も聞いてもらえなくなる……そう予感しながらも、海月は雪之助をまっすぐ見て言った。
「俺は、雪之助を一人にしたくないよ。雪之助がその資格はないって思ってたとしても、俺の教育係は雪之助だけだ」
一瞬、雪之助の鍬を動かす手が止まった。
「……好きにしなよ」
横顔は髪に隠れて見えなかったが、土を耕しながら投げられたその言葉に海月を拒絶する色はなかった。
「ただしうちに来るつもりなら、少しは手伝ってもらうからな」
「勿論!」
海月は安堵していた。雪之助は姿を消すつもりがないこと、そして何より雪之助から拒絶されなかったこと。
「じゃあ何から手伝えば良い?」
身を乗り出して尋ねると、雪之助は顔を上げた。そして呆れ顔で睨まれる。
「……一旦帰って沖之丞さんに謝って来い。今は剣術稽古の時間だろ」
こんな感じの導入の雪之助と海月の小説本を9月のミラフェスで出したいと思ってます。
今の予定だとブロマンス止まりだと思う多分(自信がない)