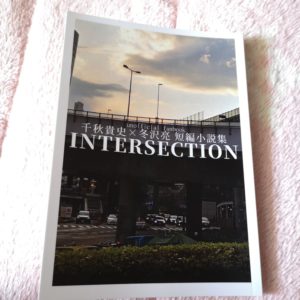高校を卒業して劇団に所属し、劇団での活動の傍らで縁に恵まれたことをきっかけに芸能界でも多少活動するようになり、そうして何年か過ごしてみれば、いつの間にか自分の誕生日がそう特別な日ではなくなっていることに気付くのにそう時間は掛からなかった。
それでも自分が生まれた日を毎年祝ってくれるような人、例えば家族から届くメッセージを見れば自分の誕生日は少し特別になる。SNSに届くファンからのメッセージや、劇団に届くプレゼント──それは年々増えている──を見れば、自分が生まれたことを祝ってくれる人はこんなにも沢山いるのだと実感して、胸が熱くなる。
だがそれはそれとして、誕生日だからと自分から特別なことをするというつもりはなく、千秋はいつも通りに劇団の稽古や仕事に励む。むしろ外から言われるまで自分の誕生日というものを忘れていることすらある。
今年の誕生日当日は、朝から夜まで地方での仕事。仕事では初めての一日がかりの地方遠征となるが、千秋はその前日も必要以上に気負うことなくいつも通りに過ごしていた。自分の誕生日前日という意識もなく。
そう、いつも通りに、冬沢の家で料理をしていた。
「……貴史、お前今日の夜出発だろう」
「は? ああ……それがどうした」
「こんなところで油を売っていていいのか?」
「油っ……」
思いがけない方面から飛んできた言葉の棘に、千秋はエリンギを薄切りにしていた手を止めて思わず顔を上げる。キッチンカウンター越しに腕を組んでこちらを見ている冬沢の顔は、心なしか疲れているように見えた。最近劇団以外の仕事が多くて疲れているのだろうか、と内心で気に留めながらも冬沢の質問に答える。
「……まあ、確かに俺は今日の夜に大阪行きの新幹線に乗る。だから今のうちにお前の飯を作りに来てる」
「まさか今日も作りに来るつもりでいたとは思わなかったけどね、俺は」
冬沢は深々と溜息をついてから、横目でリビングに掛かっている時計を見る。時計以上にインテリアとしての意味合いが強いウォールクロックは二時半過ぎを示していた。
冬沢の言う通り、千秋は今日の夜八時に新幹線に乗って大阪に行く。そしてホテルで一泊し、翌朝の地方ラジオ局への生出演を皮切りに夜まで大阪で仕事。東京に戻ってくるのはその日のうちだが、到着は夜十時過ぎだ。
「仕方ね―だろ、今のうちに作っとかねーと来週分作るタイミングねえし」
「いつも言っているだろう、毎週作りに来なくてもいいと……」
劇団に入って少しした頃から、千秋は冬沢の家で毎週、三品程度の作り置きおかずを作るのが日常の一部となっていた。肉が食べられない偏食家でありながら不器用で料理下手な冬沢を見かねて半ば押し掛けるような形で始めたのだが、冬沢のリクエストに応えるのが思いの外楽しくて習慣化してしまった。
毎週そこまでする必要はないと冬沢は毎度のように言うのだが、それでも時々リクエストはしてくれるし作った分は必ず完食してくれる。
「俺が作りたいから作ってんだよ、第一ここの台所使っていいって最初に言ったのはお前の方だぜ」
「それはそうだが話は別だ、お前は俺の面倒を見るより先に荷造りをするべきだろう」
「もうとっくに終わってるんだな、これが」
千秋が肩を竦めると冬沢は眉間に皺を寄せてから呆れたように一つ溜息をついたが、それ以上は何も言わなかった。それを了承と受け取り、千秋はまたエリンギを切り始めた。
いつも千秋が料理をしている時は、冬沢は手を出して来ない。自分が手を出しては邪魔になるだけだと思っているらしい。そしてその代わりに、キッチンカウンターの前に椅子を置いて千秋の手際をじっと見ている。料理を見て覚えようとするかの如く。初めこそ居心地の悪さを覚えた千秋だったが、いつの間にかすっかり慣れてしまった。
ちなみに冬沢が千秋を見ることで実際に料理を覚えられたのかどうかは不明である。千秋が家に来ている間は台所に立たないのだから、確かめようがない。
そうしていつも通りに千秋が料理を拵え、種類別にタッパーに詰めて冷蔵庫へ。今日は冬沢からのリクエストは特に無かったので、きのこのマリネと筑前煮、それからポテトサラダを作った。料理を終えてタッパーに詰めた頃には、時計は四時を指していた。
千秋が調理器具の片付けまで終えると、冬沢はいつものように千秋をソファに座らせて、冷蔵庫から水出しの麦茶をグラスに入れて差し出してくれる。それを受け取ってグラスをあおると、ずっと火の近くにいたことで上昇していた体温に冷たい麦茶が心地よくしみた。
「そろそろ帰るぜ」
グラスを置いて言うと、立ったままの冬沢は眉間に皺を寄せながら頷いた。
「ああ……今日もありがとう。だがそろそろ自分の都合を優先させることも覚えろ」
「だから好きでやってるしオレの都合も優先させた上で来てるんだって……」
何故こんな時まで来たのか、と言いたげな冬沢に対して気が立たないこともない。だがそれにしても今日はやけに冬沢の機嫌が悪いように見えて、そちらの方が気になった。
冬沢の機嫌が悪い時は、彼が精神的にか肉体的にかいずれにせよ疲れている時。例外もあれど基本的にはそうなのだ。すると、冬沢の顔に疲れの色が浮かんでいるように見えたのは気のせいではなかったということか。
「なんかあったのか? 疲れてるみたいだぜ」
「……何でもない」
何でもないってことはないだろ、その顔色で。
そうは思っても、こうして突っぱねてくる時の冬沢の頑なさも千秋はよく知っている。放っておくのは悪手だが、千秋に出来る事は少ない。
「……そうか。ま、しんどいようなら休める時に休めよ、劇団でオレに出来る根回しくらいなら、貸し一つでしてやる」
「っ……」
冬沢の眉がぴくりと動く。ぐっと眉を寄せたかと思うと、溜息を一つ。そして笑うしか無いとでも言うかのように、苦笑を浮かべた。
「俺は大丈夫だ。お前はもう帰って少しでも休んでいろ」
「お、おう……」
機嫌が悪いのかと思ったら珍しくこちらへの気遣いをはっきり言葉にしてくる冬沢に、どうにも調子が狂う。
いつも持参しているエプロンを鞄に放り込んでソファから立ち上がり、玄関に向かう。
「……待て、貴史」
「なんだよ?」
靴を履いたところで呼び止められる。振り返ると、眉根を寄せて何やら難しい顔をした──眉間の皺は先までよりは少ない──冬沢と目が合う。冬沢は口を開きかけて、躊躇うようにすぐ口を結んだ。だが千秋が冬沢の言葉を待っていると、やがてゆっくりとまた口を開いた。
「……難しいようであれば断れ」
「何を」
「明日」
「明日って」
珍しく要領を得ず歯切れの悪い冬沢の物言いに戸惑う。
「明日がどうした?」
続きを促すと、冬沢は意を決したような目で改めて千秋を真っ直ぐ見た。
「明日、東京に戻って来たらここまで来い。渡す物がある」
「は……?」
思いがけない冬沢の言葉に、千秋はぽかんと口を開けた。
明日の帰りが遅いのは冬沢には教えている。だが冬沢はそれを知った上で明日戻って来たらここまで来いと言っている。冬沢の家は東京駅からそう遠くないとは言え。その上渡す物がある? どういうつもりだ、と、困惑している千秋を見て、冬沢は呆れたように深々と溜息を吐いた。
「忘れたんじゃないだろうな、明日が何の日か」
「……あっ」
冬沢に言われてようやく思い出す。そうだ、明日は自分の誕生日じゃないか。
「全くお前は毎回毎回自分の誕生日も忘れて……」
呆れ果てている冬沢に「悪かったって」と笑う。
だがそれを冬沢から指摘されるのは意外なことであった。
「渡す物があるってことは、プレゼントでもくれるのか?」
「さてどうだろうね。せいぜい楽しみにしていることだ」
くすりと笑う冬沢の目の奥に悪戯な光がちらちらと踊る。冗談半分のつもりの問い掛けに思いがけず返って来たその光を見た時、どういう訳か心臓が強く跳ねた。それを誤魔化すように、無理矢理声を上げる。
「分かった。絶対来る」
思わず少し大きな声になってしまった。冬沢は驚いたように目を見張ったが、すぐにいつものような涼しい笑顔を浮かべた。それに安心したような少し惜しいような奇妙な感慨を抱きながら、千秋は一時の別れを告げる。
「じゃあ、明日な」
「ああ。また、明日」
ドアを開けてマンションの廊下に出ると、肌寒さを感じさせる秋の風がジャケットの裾を揺らした。ドアを閉め切る間際に、部屋の中で白い手がひらりと揺れるのが見えた。
完全にドアが閉まると、鍵を閉める音が静かな廊下に響く。千秋は廊下を進み、エレベーターに乗り込んだ。
たった一人きりのエレベーターで、急に頬が熱を持った。前髪をぐしゃぐしゃと掻いて、口元を押さえながら小さな声で呟く。
「明日うっかり告りそうで怖ぇな……」